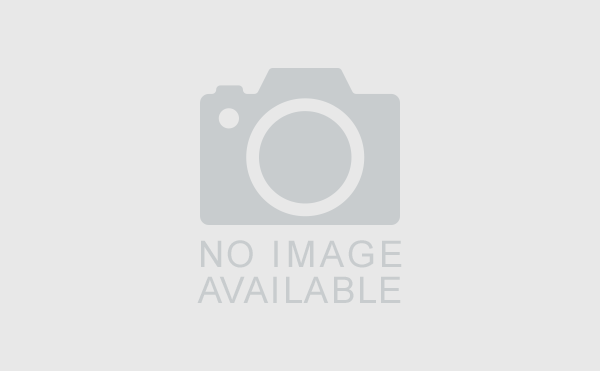建築業界の防音材(2025年6月号)
最近、ようやく鉛の遮音パネルの弊害の情報が周知されて、音楽防音室や住宅の生活防音に使用する施主が少なくなりました。
現在の防音材(遮音材・制振材・吸音材)のうち、種類が多い「遮音材」と「制振材」の概要について述べたいと思います。
【遮音材】
市販品および受注生産品の大半が、樹脂(塩ビ・合成ゴム等)を使用している遮音ゴムマット(遮音マット)やアスファルト基材を使用している遮音マットと呼ばれる遮音材として製品化されています。
*後発品は現場での検証事例が少ないため、製品選択を担当する建築士は必ずメーカーに詳細を確認してください。
*施主(相談者)は、専門業者に防音相談を申し込んで、実際に使用する防音材のサンプルを確認してください。
なお、リサイクルゴムチップを使用した遮音材は劣化が早く、性能を維持できる耐用年数が短いため、値段だけで判断しないようにしてください。遮音シートは、多くのメーカーの施工要領が間違っているため、お勧めできませんが、使用する場合は、専門業者の指導を受けてください。
【制振材】
制振材の大半が、建築業界以外で開発された製品をベースにして製品化されていますが、免震構造や二重床の防振ゴムを除くと、共振(同調)する周波数帯を軽視しているため、住宅や防音室の床に使用する乾式防振床を過信しないようにしてください。
典型的なのが、厚さ6ミリ以上の防振ゴムを使用した乾式防振床工法ですが、ピアノ・チェロなど楽器の固有振動数に合致して共振する現象が起きると、遮音性能が低下するだけでなく音響が悪化します。
特に、木造のピアノ防音室の音響・防音設計に際しては、実績のある専門業者に相談されることをお勧めします。
リスクの少ない製品としては、アスファルト基材を使用した制振マットや高密度フェルト材で製品化された制振フェルトがあります。
ただし、実績のある専門メーカーが少ないため、類似品を見極めることが難しいだけでなく、先発品に比べて、後発品は性能にかなり差が生じます。
また、軽量衝撃音と重量衝撃音それぞれに最適な制振材が異なるために、通常は複数の製品を重ねて設計します。
無料相談にこだわりすぎて、リスクのある防音材を使用する専門業者と安易に契約しないように注意してください。
一生の買い物は慎重に情報を入手して、必要に応じてセカンドオピニオンの防音相談(有料相談)を活用してください。
なお、防音職人では、契約案件が忙しくない時期に、初回限定の無料相談(木造案件)を行うことがあります。
予約が必要ですので、相談ページの問合せフォームでご連絡ください。※仕事場での相談打合せ又はメール・電話相談のどちらかを選択できます。いずれも、物件の間取り図が必要です。防音材選定のご相談にも対応できます。